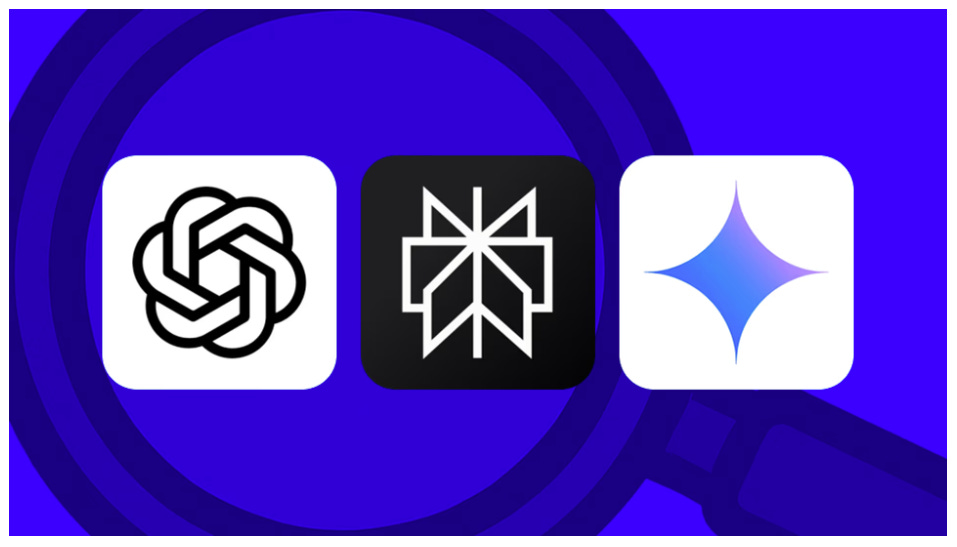「ChatGPT」「Gemini」「Perplexity」で情報収集。Deep Researchの活用例と各社の違いまとめ
「ChatGPT」「Gemini」「Perplexity」で情報収集。Deep Researchの活用例と各社の違いまとめ
https://www.businessinsider.jp/article/2505-generative-ai-deep-research-comparison/
生成AIは、私たちにとって身近な存在になってきている。「Google検索」の代わりに生成AIを使って調べ物をする人も増えた。
そして、生成AIサービスを提供する各社がいま力を入れているのは、「Deep Research」と呼ばれる新たな機能だ。
文字通り「深掘り」調査ができるDeep Researchは、「ChatGPT」を手掛けるOpenAIなどの主要なAI企業がそろって導入している。
そこで、主なサービスを一通り活用している筆者が、活用術を紹介する。また、Deep Researchの基本的な仕組みや、各社のサービスの違いもまとめた。
1. Perplexity
Perplexityはリサーチが比較的高速で、そこそこの詳しさで読みやすい文章をまとめるのが得意だ。筆者の場合、取材前に企業概要を把握するのに用いている。
実際に「株式会社メディアジーンについて教えて」と聞いたところ、わずか3分ほどで設立経緯から最新動向まで、30もの情報源から整理してくれた。ソースリンクがきちんと表示されるので、確認も簡単だ。
2. Gemini(グーグル)
Geminiは、Google検索譲りの幅広い情報収集と、表などを用いた視覚的に見やすいまとめが得意だ。
例えば、旅行の計画を立てるような使い方でその実力を感じやすい。
「熊本の博物館・美術館を巡る一日プラン」を作成してもらったところ、最初に「計画を立てます」と宣言し、段階的に情報を整理していった。
Geminiの場合、成果物はGoogleドキュメントに書き出せる。
また、ポッドキャスト風の「音声概要」、視覚的に分かりやすい「インフォグラフィック」に変換する機能も備えている。
3. ChatGPT(OpenAI)
ChatGPTは、制作に時間がかかるが詳しく情報を網羅した調査結果を出してくる傾向がある。政府文書や海外の記事まで、多様なソースを踏まえてまとめてくれる。複雑な業界の動きなどをまとめる用途もそつなくこなせる。
今回は「2019年以降の携帯電話業界の動向」について調べてみた。
ChatGPTは13分かけて142回もの検索を重ね、24の情報源から「大手4社の戦略変更」「MVNO市場の変化」「端末メーカーの動向」といった切り口で、1万3000字程度のレポートを作成してくれた。
調査中の待ち時間は気になるが、じっくり腰を据えた調査には頼りになる。
調査に時間で選ぶなら、
すぐに結果が欲しい:Perplexity
少し待てる:Gemini
じっくり調べたい:ChatGPT
調査内容で選ぶなら、
企業情報を手早く把握:Perplexity
計画を立てる、情報を整理:Gemini
業界動向を深く分析:ChatGPT
そして、これらを組み合わせて使うと効率がさらにアップする。